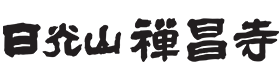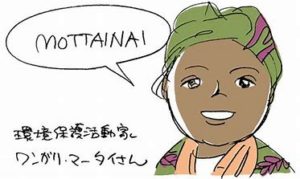平成31年3月17日(日)、天候にも恵まれ、以下の通り当山毎年恒例行事のひとつである『春季彼岸会法要および、護寺会総会』を開催させて頂きました。
なお、この度は彼岸会法要に続き、山形県見竜寺のご住職 池田好斎老師を法話講師にお招きして、大変有難いご講話を頂戴致しました(老師御家族の実体験に基づいた感動秘話など、大変貴重且つ、有意義なお話であったかと存じます)。
多くの皆様方のご参列により、この度も無事に執り行うことが出来ました。これもひとえに皆様のご協力の賜でございます。この場をお借りして、御礼申し上げます。 「どうもありがとうございました。」
 春季彼岸会法要
春季彼岸会法要
 山形県 見竜寺ご住職 池田好斎老師
山形県 見竜寺ご住職 池田好斎老師
 護寺会総会
護寺会総会 護持会総会
護持会総会 合掌
平素は禅昌寺護持に御協力を頂き、感謝申し上げます。
当寺では下記の通り、春季彼岸会法要並びに、護持会総会を開催いたします。 3月17日は禅昌寺が1615年に創建された記念日です。皆様お揃いでお参り下さるようご案内致します。
記
一、日 時 平成31年3月17日 日曜日 午前10時半より 春季彼岸会法要・護持会総会 済み次第懇親会
◎ 春季彼岸会法要
◎ 平成31年度禅昌寺護寺会総会 ※お彼岸会法要に引き続き開催致します。
一、議題
平成30年度事業報告・決算報告・監査報告
平成31年度事業計画・予算案・その他
合掌

禅昌寺庭園(中庭)の梅の花が見事に咲きました。
今年はちょうど3月3日の桃の節句(ひなまつり)に見頃を迎えており、これから春に向かって、新天皇の御即位や新しい年号の制定など、縁起の良い季節が訪れる兆しが見えています。

本年も例年通り2月28日に愛知専門尼僧堂堂長であられる青山俊董老師をお迎えし、昼食をはさんだ午前の部(10時30分~12時)と午後の部(13時30分~15時)の計3時間ほどのお時間を頂戴して、『さわやか講座』を開催させていただきました。
この度のテーマは『正法眼蔵 八大人覚(お釈迦様のご遺言)』と云うことで、お釈迦様の最後の教え(遺言)を説いた内容に基づき、とても解り易く有難いご高話と大変貴重な御説法を賜りました。
なお、老師のご希望により、本年より9月の講座は行わず毎年2月(28日)の年一回開催となりますことをご了承下さいますよう、宜しくお願い致します。※来年のご講演テーマは、『魔訶般若波羅蜜多心経』を予定致しております。


各位
時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
昨秋(平成30年9月30日予定)は台風の影響により、止む無く中止とさせていただきました青山俊董老師『さわやか講座』ですが、皆様方からの強いご希望により、例年通り、以下の日時にて開催させていただく運びとなりました。
日 時:平成31年2月28日 木曜日
午前の部 10時30分~12時
午後の部 13時30分~15時
講 師:青山俊董老師( 愛知専門尼僧堂堂長)
講 本:『正法眼蔵 八大人覚(しょうぼうげんぞう はちだいにんかく)』※ お釈迦様の遺言
参加費 :午前・午後各千円・昼食代100円
場 所 :禅昌寺講堂
※ 参加ご希望のお方は、昼食等の準備が有りますので、電話番号 ☎ 082-229-0618番までお申し込み下さい。
※ 午前・午後のみのご参加も可能です。
お友達と誘い合ってご参加下さい。
732-0002 広島市東区戸坂山根3-2-7
禅昌寺道心会
この度、境内(本堂・玄関前)に植えられている灌木の剪定を行いました。
丸く奇麗な形に成型して頂き、見る目にも優美さを感じます。




合掌
各位
時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
本日(平成30年9月30日 13:30~)開催予定の青山俊董老師『さわやか講座』ですが、大型で非常に強い台風24号が勢力を維持したまま、九州から四国・西日本地域に接近するとの予報を受け、交通事情および参加者の安全等を考慮した結果、止む無く中止させていただくことと致しましたので、お知らせいたします。
開催を心待ちにしておられた方々には、大変残念な結果となり、また講演当日のご案内となりましたことを、心より深くお詫び申し上げます。
尚、次回の講演につきましては、開催が決定しました際に改めてご案内いたしますので、ご了承のほど、よろしくお願いいたします。
合掌
今夏の酷暑も次第に和らぎ始め、清々しい秋の訪れを心待ちにする季節となりました!! 当山においても、お盆法要からお彼岸法要に至るまでの間、現在一段落ついている状況です。この期間を利用して、以前より検討されていた本堂前庭(山門から本堂および玄関へと続く)敷石の改修工事を実施しております。※以下の写真をご覧ください。






皆様方には、ほんの少しの間ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承のほど、宜しくお願い致します。
合掌
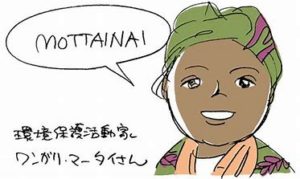
「お盆」を迎える前に、皆様にぜひ知っておいて頂きたい言葉として、「施食(せじき)= 別の呼び方では、お施餓鬼(せがき)」がございます。つまり「施食」とは「餓鬼に施す」という意味に通じます。
※「餓鬼(がき)= 生前の悪行の報いによって、六道(天上・人間・修羅・畜生・餓鬼・地獄)の一つである ” 餓鬼道(がきどう)” に堕ちた亡者のことを云います。
この餓鬼道に堕ちて苦しんでいる無縁仏様を供養する法要が施食会(せじきえ)です。当山では、ご先祖さまの霊を供養するお盆の法要と合わせて、例年『盂蘭盆施食会(うらぼんせじきえ)法要』として執り行わせていただいております。
曹洞宗をはじめとする禅宗では、「生飯(さば)」という施食作法があり、これは食事のときに七粒ほどの米粒を供養するもので、これにより供養されない亡者(もうじゃ)や、生前に犯した罪によって飢え苦しむ餓鬼道に堕ちた仏様に施す作法です。もし宜しければ、頭の片隅にでも入れておいてください。
上記の内容を踏まえて...この度の本題に移りますが、さて皆さん「食品ロス」という言葉をご存じですか?
まだ食べられるのに廃棄されてしまう(無駄にする=ロスする)食品のことを言います。日本では、年間646万トンもの食品ロスがあると推計されています。国民一人あたり、毎日お茶腕1杯分のご飯が食べられずに捨てられている計算になるそうです。※今もなお、8億1500万人(世界人口の9人に1人)が飢餓で苦しんでいる状況にも関わらずです。
例えば、皆さんも宴会でお開きになり席を立つ時に、食べきれずに残された料理を目にして「もったいない」と感じたことがありませんか?これらも食品ロスに当たります。そんな食べ残される料理をできるだけ減らすのを目的に、地方のある自治体では数年前から「30・10(さんまる・いちまる)運動」という取り組みが行われています。宴会の乾杯から30分間はお酌などで席を立たずにまずは料理を楽しみ、そしてお開きの10分前には自分の席に戻り残った料理をいただきましょう!と呼びかける運動です。
※因みに、現在世界共通言語となった「MOTTAINAI(もったいない)」の語源は、そもそも仏教に由来しています。
以下、<ウィキペディア(フリー百科事典リンク)より引用開始>
もったいない(勿体無い)とは、仏教用語の「物体(もったい)」の消失を意味するものであり、物の本来あるべき姿がなくなるのを惜しみ、嘆く気持ちを表しています。元来、「不都合である」、「かたじけない」などの意味で使用されていた言葉が転じて、現在では、一般的に「物の価値を十分に活かし切れておらず、無駄になっている」状態やそのような状態にしてしまう行為を戒める意味で使用されています。<引用終了>
日頃から食事は必要な分だけ用意し、それを残さずいただくことが大切です。万物(食べ物一つ一つ)の命をいただいて、自分の生命が成り立っていることをしっかりと受け止め、食べ物を粗末にしないように心掛けて参りましょう!!
それでは、手と手を合わせて「いただきます!」
合掌